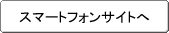去年の秋ごろから、私にとっての大問題は”珈琲豆 ”の確保であった。 新しい「珈琲豆」の購入先を、如何にして確保するかの問題で、端からすれば大した問題ではないかも知れない。 もちろん生き死にに関わるような大問題ではないし、たかが珈琲豆の問題でしかない。 とはいえ、毎日の様に珈琲を淹れて飲む習慣の私にとっては、旨い珈琲を飲めるかどうかは、大きな問題なのである。 発端はここ20年近く贔屓にしていた「キリマンジェロの豆」が、手に入らなくなったことである。 珈琲豆が高騰している事はここ数年続いていて、諸物価の高騰や珈琲豆の生産が不作続きで、多少の価格が上がることはある程度覚悟はしていた。 しかしだからと言って、供給先である食品スーパーがプライベートブランド(PB)のオリジナル珈琲豆の生産を、止める事態に迄陥るとは考えていなかった。 それまでは200g当り、5・600円で購入する事が出来たのであるが、高騰しても7・800円くらいで収まるかと、推測をしていたのである。 ところがそのPB商品の生産そのものを、止めてしまったのである。 いつもの陳列棚にそのPB商品は無く、何処のスーパーでも売ってる、ナショナルブランド(NB)の珈琲豆しかお目にかかれなくなっているのである。 残念である。 その珈琲豆の魅力は、何といっても焙煎の仕方が私の好みに合っていた点にあった。 珈琲豆が黒光りするほどの深煎りではなく、ライトブラウンとでもいう煎り方で、程よい苦みに酸味が持ち味のキリマンの魅力を引き出しており、私にとって代えがたい味を味わえた。 しかもリージョナルチェーン(地域展開)の食品スーパーという事で、価格は抑え気味で、年金生活者の私にとっては旨くて財布に優しい、優等生だったのである。  しかしまぁ、商品供給が期待出来ない事が確実になってしまった以上、違うルートでの珈琲豆の確保が、当然のことながら次の課題に成るのであった。 それが去年の秋ごろの話で、以来新しい供給先の確保のために私は、少なからぬ時間を使う事に成ったのである。 二か月近く、他の食品スーパーを探し回ったが、棚に在るのは何処にでもあるナショナルブランドの珈琲豆で、その多くは『キリマンブレンド』ばかりで、私の好みには合わなかった。 次に探したのはネット通販での「珈琲豆焙煎業者」の「キリマンジェロ」探し、だった。 昨年の暮れ辺りから始め、現在も探索中なのであるが、なかなか”これだ!”という商品に出遭えないでいる。 幾つかの焙煎業者のHPの中から選んでいるのであるが、取扱商品の画面上の「書類審査」だけでは判断できないので、その都度商品を取り寄せている最中である。 私の好みに合う商品に遭遇できれば良いのであるが、なかなか都合の良いモノには出遭うことが出来ない。 従って、「お試し商品」からの修正が可能かどうかが、重要になって来る。 具体的には、当該豆を2・3回飲んだ後のフィードバック(F/B )に、当該焙煎業者が対応してくれるかどうかで、次のステップに進めるかどうかが決まるのである。 しかもこちらは「大量消費者」ではなく「少量消費者」であるので、分が悪い。 この「少量消費者」の好みに合う焙煎商品を、供給先の焙煎業者が提供してくれるかどうか、が問題なのである。 現在はまだその焙煎業者の特定には、至ってない。 しばらくはこの問題に、私の時間とエネルギーを使い続けることに成るであろう。 旨くて納得のいく業者に巡り合えるまでは、この探索が続くことをある程度は覚悟している私、である。  |
 |