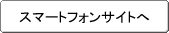源頼朝の領国の一つ越後之國の初代守護を務めた安田義資(よしすけ)公の痕跡や 足跡を求めて直江津の八坂神社や府中八幡神社、更には「上越市埋蔵文化セン ター」を訪れた私は市立図書館での資料漁りを終えた後、JR直江津駅前の居酒屋で 夕食を摂ることにした。 その居酒屋で元高校教師の郷土史研究家と知り合い直江津の八坂祇園神社の祭礼 である「祇園祭」について知ることに成る。 居酒屋で知り合った人たちの交流と情報交換から、私は安田義資公の事績や痕跡と 想える興味ある情報を、幾つか知ることが出来た。 【 目 次 】 |
高田城址に在る「高田図書館」に向かった私は、途中で軽く昼食を済ませると十三時過ぎには、高田城址に入り、城址公園内の図書館前の無料駐車場に入った。
図書館二階の閲覧室に真っすぐ向かった私は、本格的に蔵書を探し始めた。
目指す先は「郷土の歴史や資料」を取り扱っているコーナーで、ちょっとした規模の街の図書館には必ずこの手のコーナーが在るので、真っ先にそのコーナー向かったのだ。図書館の蔵書配置図で当該コーナーの位置を確認して、そのまま向かった。
当該コーナーではいつもの様に、悉皆(しっかい)調査宜しく棚に並んだ蔵書を網羅的にチェックした。
その中で気になるタイトルを見て、更に目次で確認してから面白そうな図書を何冊か確保すると、それらを持って個別に区画分けされた照明付きの閲覧机に移った。
その上で内容をチェックして、用意してきた付箋を挟んだ。
とりあえず越後や上越に残る「伝承や昔話」に類する本や「祭りや伝統芸能」に関する書物、更には「遺跡・遺構」類の書物や報告書の内容チェックを済ませ、不要と思える書籍は棚に戻した。
それから『上越市史』『(旧)直江津町史』『(旧)牧村史』といった市町村史をチェックした。『直江津町史』や『牧村史』は当然のことだが、上越市に合併する前に刊行されたものだったので古いものだった。とりわけ『直江津町史』は、私が生まれた年に刊行されたもので六十年以上前のものであった。
それらの市町村史では「通史の内、中世」に関するページや「神社・仏閣」「伝統芸能や祭り」に関するページ「遺跡や遺構」などは必ずチェックした。
一通りのチェックを終え、目が疲れてきたこともあってコピーを始めた。付箋の個所をコピーするだけの単純作業は、老眼の眼を休める事にもなったし頭も休めることが出来て、リフレッシュには役立った。
一連の作業を終えると時刻は十六時近くには成っていた。
三度目の蔵書チェックに入る前にトイレですっきりして、万全の態勢で臨んだ。
改めて午前中に「上越市埋蔵文化センター」で教えてもらった、数百ページに及ぶ上越市内の神社の詳細情報が載った『上越市史ー別編3ー』と『訂正越後頚城郡誌稿』とを探し出して、気合を入れてチェックを始めた。
「馬市」と「上越の金貨や銀貨」についての情報が記載されていた『訂正越後頚城郡誌稿』は、そんなに大変ではなかったが『上越市史ー別編3ー』の方はホントに疲れた。
八百ページ近くの同書の中から「金山神社」「八幡神社」といった神社を中心に目を通し、そのほかにも上越を代表する主要な神社についても一応チェックし、付箋を貼った。
神社関係の内容チェックを済ませただけでも、二時間は掛った。
それからチェック箇所のコピーを済ませると、すでに十九時を回っていた。閉館時間は二十時だったので慌てる必要は無かったが、とにかく腹が減って仕方なかった。
トータルで二百枚近くの分厚くなったコピーの束を抱えて、私はすっかり暗くなった高田城址公園の中の駐車場に向かった。
ひんやりとした空気と秋の虫たちの合奏が私の疲れを癒してくれた。
それから私は一路、ホテルの在るJR直江津駅前を目指した。三十分近くでホテルには着いた。途中、空腹が食事に立ち寄ることを何度も促したが、私は荒ぶるお腹をなだめながらひたすらJR駅前を目指した。それは何よりも、おいしいお酒を飲みたかったからである。
今日一日は実りの多い日であった。自分なりに充足感に満たされた日だった。こんな日は自分で自分にご褒美をあげなくては成らないのである。そのご褒美には云うまでもなくお酒は不可欠なのであった。
私は明確な目標がある場合は、その目標が達成されるまではある程度の我慢や辛抱も可能な種類の人間であったから、今回も何とかシノグことが出来た。
ホテルに戻ってコピーしてきた資料の束を机に置くと、早速街に出た。と言っても目当ての店があったわけでは無かったのだが、駅前ロータリに面するレンタカー店の近くに存在感ある佇まいが気に成っていた店が在ったので、その店に入ることにした。
店の前に置いてある看板から魚が地魚中心であったことと、地酒が多く揃っているらしい店であることが窺えたので、その店を選ぶことにした。
年季の入った外観の店の中に入ると、内もまた年季が十分感じさせられた。店の大きさは小ぶりであった。厨房を入れても30坪は無いのではないかと思われた。
1階は厨房を囲むようにカウンター席が在り、10人程度は座れそうであった。カウンター席の背後にはテーブル席が4つほど在り、八割がたは埋まっていた。盛況であった。入り口ドアの脇には二階への階段が在り、階上からは賑やかな声がしていた。
客はサラリーマン風の人達と、おなじみ客風の近隣の自営業者かと思われる人達が多かった。中には女性だけのグループもいて、女性でも安心して入れる店のようだ。
店の壁にはメニューを書いた看板や年季の入った短冊状のお品書きが、値段と共に書かれていた。明朗会計なのであろう。
スタッフは4・50代が中心で、中高年の常連客が多いのも何となく理解できた。
私はカウンター席の空いているスペースを見つけ、店の女性に指さして了解を取ったうえで、その席に座った。
おしぼりを持ってきた女性スタッフに、私は早速瓶ビールを頼んだ。
貝の煮つけのお通しと一緒に持ってきたのは、大瓶のビールであった。私は早速ビールをコップに注いで、グッと一息で飲んだ。よく冷えたビールは乾いた喉に沁みて旨かった。私はもう一杯ビールをコップに注ぎ終えると、メニュー類をよく見た。
それから「カワハギ」と「特大サザエ」「甘えび」を頼み、「茶マメ」と「ポテトサラダ」を頼んだ。ビールを飲みながら、お通しのバイ貝か何かの煮つけをつついていると、隣りの席の会話が聞こえてきた。
70前後の白髪の目立つオールバックで、ひげを生やして眼鏡をかけた知性の漂う男性と、60前後と思われる小柄で髪が相当後退している金縁メガネの男性二人であった。
小柄な男性がヒゲを生やした男性のことを呼ぶのにしきりに「先生、先生」と連発していたところを見ると、ヒゲの男性は「先生」と呼ばれる種類の人の様であった。
知的で、あまり動じそうもない目をしていたヒゲの男性は実際「先生」と呼ばれるのに相応しい風貌で、そういった雰囲気を感じさせる人物であった。
「茶マメ」と「ポテトサラダ」が運ばれてきた。「茶マメ」は枝豆の一種で、東北地方では「エダマメ」とは別に「茶マメ」といってメニューに載ってることが多い。
枝豆とは一線を画す、ある種のプライドがあるようだ。その茶マメを食べていると再び隣席の会話が聞こえてきた。小柄の男性の声は大きめであった。
「先生、オラこのまま行ったら、オラほの祭り廃れちまって誰も継いでくれる人がおらんく成ってしまうと思うと、セツナくてセツナくて・・」とコップの日本酒を飲みながら、ヒゲの先生に愚痴る様に言った。
「ん?セツナイ?」と私は「セツナイ」の意味が判らなかったが、どうやら「心配している」とか「残念だ」というような意味なのか・・。と思いながら二人の会話を聞いていた。
「若いモンが、協力的で無くなってるのか?」ヒゲの先生が尋ねると、
「それもまぁあんけんど、アネチャばっかりで跡取りのアンチャがほとんど居ねぇのさ、先生」小柄な男性はそう言ってから、また話を続けた。
「アネチャは年頃に成れば、こんだ嫁っこに行っちまって家は出てくし・・」
どうやら「アネチャ」は若い女性とか未婚の女性、という意味らしい。とすると「アンチャ」は若い男性や未婚の男性って意味なのかもしれない・・。と私は二人の話を聞きながら頭の中で二人の会話を翻訳していた。
「オマンタとこも、アネチャだけだったか?」ヒゲの先生が言った。
「そだ、二人とも嫁に出て高田と、長岡に住んでるですよ・・」と小柄な男性が応えた。
二人の会話を聞いていて私は、ここ上越でも「あなた=オマン」というのかと、ちょっと驚いた。というのは、私の父親の故郷山梨でもそう云うからであった。
身延の西島さんは今でもよく使っている。八百年前に甲斐源氏が越後の守護に成ったからといって、わずか十年足らずの支配の影響が、そのまま残っていることは無いだろうが・・。などと想っていると、こぶし大の「大きなサザエ」が、殻付きで運ばれてきた。
「殻付きのサザエ」は、刺身に成って盛られて来たのであったが、私の好きなワタ(内臓)は取り除かれており、あのちょっとした苦みのあるワタが好きな私には、残念であった。注文する時にワタをつけてもらう事を言わなかった自分を、悔いた。
「先生相変わらずお元気そうで何よりです!」店の厨房から出てきた店主と思われる四〇過ぎの恰幅の良い坊主頭の男が、前掛け姿で現れた。ヒゲの先生は相好を崩して肯くと、
「洋三、相変わらず流行っているようで、何よりだな・・」と言った。
「お知り合いで・・」と小柄な男性が小声で先生に聞いた。
「オラが商業高校で教えた生徒で、勉強せんでバイクばっか乗っててどうしようもねぇアラッポイオッチャだっただよ」と嬉しそうな顔で応えた。
「先生、若いころぁ皆そんなもんダスケ・・」と店主は笑いながらそう言って、
「今日も八坂さんの祭の件でキナッタですか?」と続けた。
「まぁ、そんなとこだ・・」ヒゲの先生が言った。
「若い衆に、祇園さんのこと色々教えてやってクンナイ」彼はそう言うとビールを1本取り出して、「オラからです・・」といって先生に注いた。ヒゲの先生は嬉しそうにコップを差し出した。
「じゃ先生、オラここで・・」店主はそう言って頭を下げると厨房に引き込んだ。
「アラッポイオッチャ」の意味はすぐには判らなかったが、「アネチャ」が若い女性で「アンチャ」が若い男性のようだから、きっとそれに似たようなもんだろうと理解した。
更に勉強そっちのけでバイクに乗ってたってことは、「アラッポイ」は「不良」とか「ヤンチャ」とかいった類いの言葉なのかもしれないと、解釈した。
いずれにしてもこのヒゲの先生は、かつて商業高校の先生をやっていて、八坂神社の「祭り」や「祇園祭」に詳しいか、またはそういった民俗学的な事に詳しい元高校教師という事らしい。
私はヒゲずらのこの元高校の先生に関心を持った。先ほどの彼らの会話から、今朝訪れた直江津八坂神社にまつわる「祇園祭」の事を二人は言っていたのだろうと、思ったからだ・・。
しばらくすると、小柄な男性が立ち上がり席を外した。トイレにでも向かったのだろうと思われた。荷物もテーブルの上も、そのままだったからだ。
私は少しの勇気を出して、ヒゲの先生に話しかけた。

「ちょっとお尋ねしますが、こちらの直江津でも祇園祭が行われているんですか?」私の問いかけにひげの先生は振り向いて、私を見定めるようにじっくり見てから、肯きながら言った。
「ハイそうですよここ上越では『上越祭り』と云ってますが、そこの八坂神社の祭礼で地元では『直江津祇園祭り』と言ってます・・」と、八坂神社の方を眼で追いながらそう言った。
「あぁ、やっぱりそうでしたか。先ほど『八坂さん』とか『祇園さん』といった言葉を漏れ聞いたものですから・・」私はそう言って小さなウエストポーチから個人名刺を取り出して言った。
「私はこういうもので、かつて鎌倉時代初期の越後之國の守護だった安田義資(よしすけ)公について、いろいろと調査・研究しているものです。民間の愛好家というか・・」と自己紹介をした。
「安田義資ですか、鎌倉時代初期の・・」ヒゲの先生は私の名刺を見ながらそう言いつつ、記憶の糸を辿っているようだった。
「ご記憶にございませんか・・。まぁ無理もないかもしれませんね、今から八百年も前のことですし、守護としての任期も10年足らずでしたからね。義資公の足跡や痕跡もあまり残ってないでしょうし・・」私がそう言うと、
「あぁ、思い出しましたよ安田義資。確か越後が頼朝の領国に成って間もない頃の守護でしたかね、一番初めの・・。で、確か頼朝につまらない事で斬首させられたとかいう・・。『吾妻鏡』にそんな事が書かれていたような・・」とヒゲの先生は思い出してくれた。
「ハイ、その通りです。そのつまらない事で斬首されたのが安田義資公です。具体的には『艶書』という、今でいうラブレター事件で、鎌倉永福寺の落成式の時に、お手伝いに来ていた女御・女房に艶書を渡した事がけしからん、とか頼朝に難くせ付けられて首を切られた、越後之國の守護だった甲斐源氏の武将、その人です義資公は・・」と私は解説した。
「その安田義資の事を調べにわざわざ東京からキナッタですか?」とヒゲの先生は好奇のまなざしで私に聞いてきた。
「ハイ、そのとおりです。その義資公の痕跡や足跡を求めて今朝も『八坂神社』や『府中八幡神社』を尋ねたり『上越市埋蔵文化センター』や『高田図書館』に行って来たところです・・」と私が応えると、ヒゲの先生は
「『八坂神社』や『府中八幡』も関係してくるですか・・」と聞いてきた。
「ア、ハイそうです。八幡神社の方は割と単純なんですよ、安田義資公は甲斐源氏の武将ですから、源氏の氏神の八幡神社には簡単に直結するんです。ご存知なように八幡神社は源氏の氏神様ですから・・」私がそう言ったところで、ヒゲの先生の連れの小柄な男性が戻って来た。私は彼に目礼をして話を続けた。
「『八坂祇園神社』も義資公、というか義資公の父親で遠江守をやっていた安田義定公が深い関わりを持っていまして・・。
それもあって先ほど『祇園祭り』の話を小耳に挟んだもんですから・・」私はそう言って義定公親子と祇園神社の関わりについて手短に話し始めた。
「安田義定公親子は平安時代末期の甲斐源氏の武将でして、兄の武田信義達と共に甲斐源氏の主力でした。信義公は甲斐源氏の嫡流でしたが、四歳下の弟が安田義定公に成ります。
因みに武田信義公は甲斐武田家の家祖でして、彼の十四代後が武田信玄に成ります。三百五十年ぐらい後の末裔ですね信玄公は・・」私はそう言って二人の顔を見てから話を続けた。
「その武田信義と安田義定の兄弟は甲斐源氏を束ねながら、治承四年の頼朝の伊豆の挙兵とほぼ同じタイミングに、木曽義仲に呼応する形で信濃平氏と源平の戦いを始めます。
この動きはいずれも、後白河法皇の息子以仁(もちひと)親王の平家討伐の令旨(りょうじ)を受けて始まった戦ですよね。ご存知だと思いますが・・」私がそう言うとヒゲの先生は、肯きながら
「越後の支配者で平氏の一門『城氏』一族は、その木曽義仲軍に信濃での戦いに敗れてまって、越後での勢力を後退させてしまいましたからね・・」と言った。
「その様ですね、城氏は都の平氏との関係が深い桓武平氏の一族でしたかね、確か・・」私がそう言うと、ヒゲの先生は大きく頷いた。
「甲斐源氏の中でも武田信義親子の主力が、諏訪や飯田辺りで信濃平氏と闘っている時、安田義定親子は主として甲斐之國に居て駿河平氏との一戦に備えていたのです。
しばらくして頼朝達が相模・駿河平氏の連合軍に『石橋山の戦い』で大敗して、安房之國に逃亡した後、その駿河と相模の平氏の連合軍が甲斐に攻め込んで来たんですよね。
で、その時に行われた富士山北麓の『波志太山の戦い』で、義定公の甲斐源氏が勝利して以来富士山西麓を実効支配しまして、それから二か月後の例の『富士川の合戦』で、平家軍を敗走させたわけです」私がそこまで話すと、傍らの小柄な男性が
「富士川の水鳥の羽ばたく音にびっくらして、一戦も交えず平家が逃げちまったっていう話だべ、まったく情ねぇ話だわな・・」と口を挟んだ。
「えぇ、おっしゃる通りです。でもまぁそれには伏線がありましてね・・」私はそう言って彼の方を見ながら話を続けた。
「その富士川の合戦の二週間程前に、富士川の支流潤井川の上出という富士山西麓で、前哨戦ともいうべき合戦がありましてね。その戦いでもう一度駿河平氏が甲斐源氏と戦って、壊滅的な敗戦を喫してしまってたんですよ。
大将の駿河之國目代橘遠茂は生け捕りにされ、副将格の長田入道親子は斬首にされ晒し首にされちゃいましてね。でその戦さの敗戦情報が、遅れて京都からやって来た数千騎の平氏方の兵士達にも伝わっていたんですよ、事前にですね・・。
その時にはたぶん尾ひれ背びれが沢山付いた流言飛語が、平氏の東征軍の中では相当飛び交っていたと思いますよ・・。
マァそんなことがあって既に浮足立っていた平氏の武人たちが、数万羽と言われた水鳥の一斉の羽ばたきに驚いて潰走した、って事らしいですね・・」と私は長々と説明をした。
「だども数万羽ってのは、さすがに話がイカイコト(大きく)ねぇスケ?」小柄な男性が言った。
「いやいやそれがあながち、そうでも無いようなんですよ。実は私も色々調べたんですが鎌倉時代の富士川の河川敷はどうやら五・六㎞近く在って、川の中瀬が十五・六瀬在ったという話です。『十六夜(いざよい)日記』に、そんな風に書かれてましてね。
ご存知なように『十六夜日記』は鎌倉時代中期に書かれた書物ですから、当時の事を割と正確に書いてあるわけです・・」私がそう言うと、二人はひとまず納得した様であった。
「信濃川もそうだども、今みてぇにダムや堰堤が出来たり治山治水が出ける前ぇの、七・八百年も前ぇの事だら、そぅだったンかも知んねえな・・」小柄な男性は肯きながらそう言った。
「ここの『関川』も昔は『荒川』って言って、だいぶ暴れ川だったサカエな・・」ヒゲの先生が伸びた顎ヒゲをいじりながら、そう言った。
「マァその様なことがあって甲斐源氏の武田信義公と安田義定公とは、その時の戦さの余勢をかって『駿河之國』と『遠江之國』に居付いて、実効支配してしまったわけです」私はそう言って話を引き戻した。
「で、どっちがどっちの領主に成ったンだべか・・」小柄な男性が聞いてきた。
「あ、失礼しました。『駿河之國』を武田信義公が、そして『遠江之國』を安田義定公が領国として治めたわけです」私がそう言うとヒゲの先生が、
「確かにその様でしたが、あまり長くは無かったんでなかったですか、特に武田信義の駿河支配は・・」彼はそう言って私に確認してきた。
「あはぃ、おっしゃる通りです。信義公の武田氏が駿河を支配していたのは二・三年間でしたかね、確か・・。でその後は北条時政に守護が変わってしまいましたからね・・。
因みに義定公は十四・五年間遠江守をやってましたですね・・」私はそう言ってヒゲの先生の話を補足した。
「なるほど・・。ところで安田義資は・・」先生が私に聞いてきた。
「あ、そうでした肝心の義資公についてですね・・失礼しました。彼はその後の一ノ谷の戦いを始めとした、西国での平家追討に活躍しましてその褒賞として、頼朝によってここ越後之国の守護に任命されたわけです・・」私はそう言った。
「文治元年、でしたかね確か・・」ヒゲの先生が呟いた。
「おっしゃる通りですね、西暦だと1185年ですね・・」私が続いた。
「その当時父親の安田義定公は遠江守をしてまして、信濃守をしていたのが義定公の弟の加賀美遠光で、ちょうどフォッサマグナと同じように糸魚川のある上越から、信濃・甲斐更に遠江と日本海から太平洋まで日本列島を縦断する形で、甲斐源氏が守護として統治していたわけですね。
云ってみれば鎌倉幕府のある関東の、西国や北陸に対峙するその最前線に甲斐源氏を配置した様な構図に成るわけです。これってちょっと面白いですね・・」と私が言うと、
「確かに、そういうことに成りそうですね、まぁ甲斐源氏の視点で見ればでしょうが・・」とヒゲの先生はそう言って、肯いた。
「当時は北陸も含めて、三河・美濃・飛騨以西にはまだまだ平氏の勢力がしっかりと残っていましたからね・・。そもそも西国は平氏の本来の地盤ですし、五年や十年くらいの源平の戦いでそれまで数百年に亘って築かれてきた、平氏の強力なネットワークや基盤は、簡単には崩れなかったと思いますよ・・」私がそう言うと、ヒゲの先生は
「朝廷の動きも、まだまだ不穏だったしな。いつまた源氏追討の令旨が出るかも判らなかったでしょ、京の情勢次第では・・。確か頼朝は後白河法皇の事を『日本一の大天狗』と言ってたかと・・」と、顎ヒゲをいじりながらそう言ってニヤッとした。
「あはは、そうでしたね。後白河法皇はキャラが際立ってましたから『大天狗』でもあったし『大タヌキ』でもあったと思いますよ、彼は・・」私もニヤニヤしながらそう言った。
「あっきゃぁ~、そうなんかい。後白河法皇ってのはそいガ、おもしれぇ法皇様だったのケ?」小柄な男性が興味津々といった面持ちでそう言った。
「そだ、ほれは間違いねぇ。若い頃は『今様』って言って、当時の流行歌を毎日遅くまで練習して喉が腫れあがって、血反吐はくまで歌ったちゅうくらいの今様狂いで、早くっから天皇の後継レースからは外された、ちゅう御仁だわ」ヒゲの先生がニコニコと解説した。
「でしたね、それに熱中すると入れあげるって性格は、今様に限らず『熊野詣で』でも同じでしたね。生涯に三十数回も熊野には詣でているというくらいの熱の入れようで・・」私がニヤリとしながらそう言うと、
「三十数回もかぇほりゃ凄い。『今様狂い』に『熊野狂い』だべな、そりゃ・・」と、あきれたように小柄な男性は言いつつも、嬉しそうにニコニコしながら日本酒を呑んだ。
「話は変わりますが、その安田義定公親子の領国の経営に、他の國では見られないような特徴が幾つかありましてね・・」私はそう言って、二人の顔をじっと見て言った。
「当時の事ですからコメの生産を基本にした荘園経営が、領国経営の基本であることには変わりないんですが、義定公親子の場合はそれに付加して『騎馬武者用の軍馬の畜産・育成』と『金山開発』とが加わるんですよ」私がそう言うと、
「軍馬の育成は当時の鎌倉武士というか東国の武者達は皆、力を注いでいたでなかったですか・・。木曽義仲にしたところで、やっぱり騎馬武者でしたしね・・」ヒゲの先生はそう言って、私の説に疑問を呈した。
「ハイ、おっしゃる通りです。義定公に限らずだと思います当時は・・。ただ甲斐の場合はその騎馬武者の伝統というか歴史が他国とは桁違いで、四世紀の頃からすでに始まっていたんですよ。
馬の歯や骨などの遺物や馬具が、当時の遺跡や古墳などからも見つかっているくらい古くて、有名な聖徳太子の『甲斐の黒駒』の伝説や、日本書紀の壬申の乱の際の『甲斐の勇者』にも登場するくらい、年季が入っているわけです。
ですから騎馬武者文化は甲斐之國では十二世紀の当時からしても、すでに七・八百年以上前から続いているわけでして、とにかく歴史が古いんです。甲斐の騎馬武者の伝統は・・」私はやや自慢げにそう言った。
「なるほど、そんなに古くから続いてるんでしたか・・。いや、勉強に成ります・・」ヒゲの先生はそう言って、私に先ほどの店主からのおごりのビールを注いでくれた。
「あ、すいません。ご馳走に成ります・・」私はそう言ってビールを注いで貰ってから、お返しに自分のビールを注ごうとするとヒゲの先生は
「私はモッパラ、こちらなんで・・」と言って日本酒の入ったぐい飲みを持ち上げ、やんわり断ってから、続けて
「ところで『金山開発』の方は・・」と私に聞いてきた。
「そうでしたね『金山開発』についてはですね、やはり甲斐之國では昔から金山開発が有名ですし、伝統もあるんです・・」私はそう言ってからビールを一口飲んだ。
「有名なのは武田信玄の時代の金山開発なんですが、これもまた騎馬武者同様信玄公の頃が最も盛んではあるんですけど、やはりその先駆けは安田義定公に行きつくんです。
甲州金山の担い手は、昔から黒川衆という名の金山(かなやま)衆が有名なんですが、その黒川衆は義定公の領地の金山開発の職能集団なんです。
大菩薩峠という中里介山の小説でも有名な二千m級の山近くの金山で、そこは黒川金山と云うんですがそこもまた義定公の領地で、義定公が積極的に登用して育成していたのがその黒川衆だったんです」私はそう言って、二人を観た。
「『金山衆』って何だべさ?」小柄な男性が呟くように言った。
「『金山衆』ですか?そうですね、金山開発のスペシャリストというか鉱山開発の専門家集団ですね、一言で言うと・・」私が言った。
「へぇ、佐渡金山の頃よかずっと前ぇってことに成るだスケ?ほうしたら・・」と彼が言った。私は肯いて、
「佐渡金山の奉行大久保長安も黒川衆の仲間で、武田家滅亡後徳川に仕えた金山開発のスペシャリストだったんですよ」と説明した。
「えっ⁉ホントだべか?」小柄な男性はそう言ってから、ヒゲの先生に確かめるように、顔を観た。
「それは間違いありません」私はきっぱりとそう言い切って、さらに話を続けた。
「まず金山の埋蔵量は無尽蔵にあるわけではないんですよね、当たり前って言えば当たり前ですが。大体一つの鉱脈だとかなり大きな金鉱脈でも数十年間しか持たないようですね、数十年でだいたい採り尽くしてしまうらしい、ようです・・。
で、彼らはそれからの行動が枝分かれするらしいんです。新たな金鉱脈を探しに自ら他所の山に金の鉱脈を探しに行くとか、豊臣秀吉とか徳川家康のように金山開発に熱心な権力者に雇われて行く、とかですね。
ほかには鉱山開発で培った技術・ノウハウをもって治山・治水の土木関係の仕事に就くとか、いろいろ分かれて行くみたいですね。
まぁ彼らにしても生活して行かなきゃなりませんから、自然な事ですけどね・・。で、大久保長安の場合は徳川家康に金山奉行として仕えた、って訳です・・」私はそう言ってヒゲの先生達を見た。
「なるほどそうでしたか、大久保長安もその黒川衆のメンバーだったわけですか・・」ヒゲの先生が肯きながらそう言った。続けて、
「ところでその安田義資と祇園祭とは・・」と言って話を戻した。
「あぁ、そうでしたね肝心な事を忘れてました、すみません・・」私はそう言ってから義定公親子と祇園祭との関わりを説明した。
「義資公が越後之國の初代守護に成ったのは二七歳ぐらいの事で、まだまだ若くてとても独りで、越後之國の守護を務めるには力不足だったと思います。
それで実際には父親の遠江之守義定公の力を相当借りていたと思われます」私はそう言ってからビールを一口飲んで、話を続けた。
「その義定公は後白河法皇の勅命を受けて、八坂の祇園神社や伏見稲荷大社の本殿や拝殿、楼門といった主要な施設の建て替えや造築をやらされているんですね、文治三年から六年頃の事ですが・・」
「文治って言ったら、西暦だら何年頃に成るんだべ・・」小柄な男性が呟いた。
「そうですね西暦だと1187年から89年ころだと思います。今からざっと830年くらい前に成りますかね・・」私が応えた。
「その八坂祇園神社や伏見稲荷の造築や建て替えと、何か関係があるわけですか?祇園祭が・・」ヒゲの先生が尋ねて来た。
「あ、はいその通りです。義定公を初めとした義定公の家来達、武家の家来衆と先ほどの黒川衆の家来達の職能集団とが、祇園祭の山・鉾である『八幡山』『綾傘鉾』に実は大きく関わってまして、八坂の祇園祭につながって来るんです・・」私は応えた。
「祇園祭に、武家や職能集団がですか?確か町衆が深く関わって来たのではなかったですか、京都の祇園祭も・・」ヒゲの先生が突っ込んできた。
「はいおっしゃる通りです。町衆が関わってきます。ただしそれは京都の洛中の殆どが灰塵に帰したと言われている応仁の乱以降の事なんです。町衆が前面に出てくるのは・・。
で、その応仁の乱以前は、むしろ武家衆や朝廷に使えていた大舎人(とねり)といった織部の職能集団や、洛外の摂津山崎や久世の地域の住民などが深く関わっていたようなんですね。
応仁の乱以前の祇園祭の様子が書いてある伏見宮親王の『看聞日記』等には、そういった事がハッキリと書かれていまして、町衆が主役に成るのはやはり応仁の乱以降の事なんです・・」私は断定的にそう言った。
「なるほどそうでしたか、応仁の乱の前と後では祇園祭の担い手が大きく替わって来るわけですか・・。いや、勉強に成ります・・」ヒゲの先生はそう言って私のコップにまたビールを注いだ。私はお礼を言ってコップのビールを一口飲んで喉を潤してから、また続けた。
「ですから鎌倉時代の初期だと、祇園神社に祀られている大小さまざまなお宮の祭神を信仰する人達が、それぞれ組というか阿波踊りの連のようなものを作って、各々の関係場所から八坂の祇園神社に向かって風流(ふりゅう)舞を踊ったり、練り歩いたという事なんです。
その際甲斐源氏の義定公の家来である武家衆は、祇園神社に祀られていた『八幡宮』に向かって『八幡山』を曳いたわけです。
一方同じ義定公の家来である金山衆の方は、祇園神社内の金山彦を祀った『金峰山宮』に向かって、『綾傘鉾』のチームを組織して踊り練り歩いた、というわけです」私はそう補完説明をした。
「だけんがそれが直江津の祇園祭とどう、関わって来るんだべ・・」小柄な男性が呟いた。
「そうですねこれは私の仮説なんですが、この直江津に八坂神社を勧進し祇園祭を導入したのは、義定公の意向を受けた義資公だったのではないかと、そんな風に想ってまして・・」私がそう言うと小柄な男性は、
「先生、ほんとだべか・・」とヒゲの先生に向かって聞いた。
「いやいつ頃から始まったかの確説は無いんが、平安時代ではないかと云われてはいるんだ・・。立花さん、あなたがそう思われる根拠といいますか理由は何ですか?」ヒゲの先生が口調を改めて、そう言った。
「そうですね、その理由というか根拠は幾つかあります。まずは、先ほども言いましたが義定公と京都祇園神社との関係の深さでして、両者はつながりがとても深かったんです。大規模な造築や建て替えを通じて、ですね・・。
それに義定公は自身の主な領国や領地には殆ど全部と云って良いくらいに、祇園神社や伏見稲荷神社を勧進してるんですよね、本拠地の『甲斐之國の牧之荘』はもちろん『遠江之國の浅羽之荘』や『森町飯田』辺りでもですね・・。
次には河川の氾濫が関係してきます。ここ直江津も『関川』を初め『飯田川』『保倉川』といった河川が集約して日本海に注いでますよね。で、治山治水の未発達な当時だと大雨が続いたり台風がやって来ると河川は暴れ川に成って、洪水や氾濫を繰り返したと思うんです。
その河川の氾濫や洪水は同時に感染病や疫病などをもたらして来たと、私は想います・・」私がそう言うと、小柄な男性は何か思い当たる事があるのか、納得するように何度も大きく肯いた。ヒゲの先生は、
「確かにそうですおっしゃる通りです、よくご存じですね・・。関川は昔、荒川と云われておって、大雨が上流で降るとよく氾濫しておったようです。飯田川も保倉川もまたしかりでして・・」と肯きながらそう言った。
「近代以前の治山治水の土木技術では、全国的に大きな河川の流域はだいたい似たようなものだったと、そう思います。いずれにしてもそういう地理的な背景があって、疫病や感染病を封じるために祇園神社が勧進され、またそれを受け入れる土壌があったんだと思います、この直江津にも・・。
ひょっとしたら義資公の領国に成る以前から、祇園神社が祀られていた可能性も否定はできませんがね・・。
更にこれが一番の理由ではないかと私は想ってますが、義定公はかなりお祭りが好きな武将でしてね。甲斐之國牧之荘はもちろん富士山西麓や遠江之國などでも、盛んに神事やお祭りを奨励し、実施してきたようなんです。
具体的には『流鏑馬の神事』や『精霊を供養する盆踊り』に加え『祇園祭』等もその例なんです」私が言った。
「その武将はそんなにお祭り好きなんだかゃ?」小柄な男性は嬉しそうな顔でそう言った。
「ハイ相当・・お祭り好きだったようですね彼は、あはは・・。もちろんそこには領民の人心掌握のためといった、新しく入部・入郷して来た領主としての計算も働いていたと思いますが、義定公は元々お祭りが好きな性分のようですね・・。
本拠地の甲斐之國はもちろんの事、新しく領地や領国にした場所ではいずれも、盛んに神事や祭りを執り行っているんです。
そしてありがたい事にそれらの神事や祭りは、それぞれの地域や地元に多くの場合定着してまして・・。そのおかげで私なんかが八百年も前の義定公の痕跡や足跡を知るのに役立ってまして・・。
それらの神事やお祭りをヒントにして、当時の事に辿って行くことも可能に成ってるんですけどね・・」私は長々とそのように説明した。
その間ヒゲの先生はじっと黙って、私の説明を聞いていた。
「直江津甚句」
アエ―エ
参らんしょうや 地蔵さんの縁日だ
ア 踊らにゃノオ 婿やらぬ 嫁さは御化粧がすきだ
ア 今朝またノオ 水かがみ アリャサのヤッサ
アエ―エ
見えた見えた 白帆が見えた
ア 黄金咲くノオ 山見えた かけ橋架けたらよかろう
ア 四十五里ノオ 波の上 アリャサのヤッサ
この甚句で歌われている「黄金咲く山」とは、糸魚川や青海辺りに点在した「金山」を指しているのだろうか・・。

しばらく黙って私の話を聞いていたヒゲの先生が、やっと口を開いた。
「なるほどな、そういう考えもあるかもしらんね・・。軽々には言えんでしょうが、平安時代から続いたと云われている祇園祭ではありますが、それを明確に示す古文書や遺物は残ってないんですよ。
ましてや戦国時代末期の『御館(おたて)の乱』で、直江津の由緒ある神社・仏閣に伝わる古文書などはそん時に、殆どが消失や消滅してるもんでね・・」先生は手元の日本酒をぐい吞みに注いでから、また話を続けた。
「越後之國が越中から分離し一国として認められ、現在の県域に近い形が確定されるように成ったのも、八世紀の和銅五年の事でしてね、奈良時代や平安初期にはまだまだ蝦夷との戦いが続く、陸奥のエリアの一画でしたから越後は・・。
それに関川をはじめ信濃川や阿賀野川の下流域は、太古より大雨や台風の度に氾濫を繰り返して、その水も砂丘によって堰き止められ多くの巨大な潟(せき)湖が点在し、国としては未整備な状態がまだまだ続いておって、安定せんかった時代がずっとでしたからね・・。
それでもやっと平安時代の後期頃に成って落ち着きだして、摂関家や奈良・京都の大寺院や有力な神社・仏閣の荘園が出来て新田開発が進み、少しずつ都の文化が入って来たです。
きっとそんな頃に祇園神社や祇園祭も入って来たのではないかと、私などは考えてましてね・・」ヒゲの先生が語った。
「そういえば越後之國の国衙や国分寺・国分尼寺の場所はまだ、特定されていないとか・・。確か全国でも唯一・・」私がそう話すと、
「おっしゃる通りです。現在国分寺として確認出来得る五智国分寺も、室町末期の戦国期に謙信公が勧進・創建したと云われてましてね。それだと他国のような奈良時代や平安時代とは七・八百年は時代が下ってしまいますからね・・」ヒゲの先生が言った。
「そのようですね・・。でも府中八幡神社が直江津に在るという事は、やっぱりこの辺りに国分寺や国衙が在ったと推測する事は出来ませんか・・」私がそう言うと小柄な男性が、
「八幡様と、国分寺になんか関係あるダスケ?」と聞いてきた。
「あはぃ、関係あります。府中八幡神社は国分寺を武によって守護するという役割があって、元来国分寺や国衙の近くに配置されることが多かったんですよ。そういう役割を持った神社でして・・」私がそのように説明した。ヒゲの先生は肯きながら聞いていたが、
「ただね、立花さん。どうやら一等初めの頃の国分寺は五智国分寺の辺でなくて、三郷の長者原辺りでないかってせう(そう)いう説が有力でね、オラなんかもそう思ってる一人ですよ・・」と先生が言った。
「何か考古学的な遺跡や遺物でも、出て来てるんですか・・」私がそう確認すると、
「国分寺によくみられる礎石が、三郷地区の長者原の長者屋敷からいくつも見つかってるですよ。布目瓦や丸瓦の破片なんかも長者原の近隣で沢山出土してます。これらは奈良時代のものでしてね・・。
それに大正時代に作られた『三郷村史』に長者原周辺には、条里に基づく井田の形跡が多く残っている、といった事なんかも書かれてましてね。
あれやこれやを総合すると三郷の長者原界隈に国分寺や国衙が在ったんでないかって、まぁ客観的にもそう推測する事が出来るわけですよ。それに八幡神社も近くに在ったりしますし・・。
あ、それから先ほどの国分寺と八幡神社との関係は若干訂正が必要かと思います。
国分寺を守護する八幡宮は『国分寺八幡宮』と言って将に国分寺に付属しているでしょうが、直江津八幡宮の様に『府中八幡神社』と云われる場合は、越後之國八幡宮の惣社として、越後國内の八幡宮全体を統べる役割を担っている神社だと思います、念のため・・」ヒゲの先生は私の誤りを指摘しつつ、詳しく解説してくれた。
「なるほど、そういう事でしたか・・。いやありがとうございます、勉強に成ります・・。おっしゃるように越後之國の最初の國府がその三郷地区に在ったとすると、奈良時代や平安時代には、国衙や国分寺はその三郷の長者原界隈に在った、という事に成る訳ですね。
それから何かのきっかけがあって、現在の五智国分寺辺りに移ったと・・」私が言った。
「んだ、謙信公が戦国時代に春日山や御館に近い五智に移しなさっただ・・」小柄な男性が肯きながら、そう言い切った。
「そうなんですか・・、でもそうすると直江津の府中八幡の存在や、祇園神社の件がちょっと説明がつかなくなりませんか、確か両神社とも創建はそれぞれ平安時代後期だとか・・」私は今朝見て来た二つの神社を思い出しながら、そう言った。
「そうですね、せう(そう)いう問題がまだまだ残ってますね。実際のところ越後に限らずですが、鎌倉時代の頃には全国の國衙跡や國分寺はだいぶ廃れてしまっていたと『吾妻鏡』なんかにも書かれていたような状態でした。
奈良時代や平安時代に造られた國府や國分寺なども、創建当初のような威容は保て無くなったみてぇですからね・・」ヒゲの先生が言った。
「でしょうね、鎌倉時代でも創建してから五・六百年は経ってますからね、その間に大地震や台風などの風水害にも見舞われているでしょうし、日本海からの厳しい風雪にも晒されているわけでしょう。
しっかりした補修や改築といった事が継続的に行われない限り、廃れてしまう方が当たり前と言えば当たり前で・・」私が言った。
「その通りです、越後之國の國府や國分寺・國分尼寺はさっきもせう言ったように、奈良時代に初めて創られた頃は三郷辺りだと思ってほぼ間違いないと思いますよ。
それから謙信公の五智国分寺までの間に國府の場所が変わった可能性もあるし、その間に新たに造られたとしてその場所が、替わってしまった可能性だってあると思う事も出来るわけですよ・・」ヒゲの先生が言った。
「ひょっとしてそれって、信濃の国府と同じってことですか?確か信濃の國府・國分寺は当初は今の上田市に在ったのが、あとで松本に移ってしまったかと・・」私がそう言った。
「えぇ、その通りで・・。オラも信濃の事も頭に在ってせう考えてみたです。それに室町時代の応仁の乱の頃、京の都が灰塵に帰してしまった時に都を離れ、関東から北陸を旅した相国寺の僧侶万里集九の旅日記に、『国分寺の堂宇は山の如く海岸に冠たり・・』などと書いてありましてね。
これは糸魚川寄りの岩殿山の事を書いてるんやないかと、オラなんかも思っておるですよ。近くに郷津の浜も在りますで・・」ヒゲの先生が言った。先生の言葉に上越言葉が混じって来た。
「岩殿山とゴウツの浜ですか・・。岩殿山はまぁいいとしてゴウツというのはどういう字を書かれるんですか?」私が尋ねると、
「郷土の郷に、津島の津だわね」小柄な男性が短く教えてくれた。
「あぁ、そちらの郷でしたか・・。でもそれと國府とは・・」さらに私が尋ねると、
「いや、郷津は國府津が転訛した言葉でないかと思ってるわけです」先生が応えた。
「あ、なるほどですね、國府津が郷津に転訛したわけですか・・。そうするとその岩殿山の近くに在るわけですねその郷津の浜は・・」私が確認すると、
「んだ。バイパス沿いの岩殿山の日本海側の麓辺りに成るんだ、郷津は・・」小柄な男性がまた教えてくれた。
「なるほどですね。そうしますと応仁の乱の頃という事であれば1470年代ですから室町の中期に成るんですかね、その万里集九の旅日記に書かれていた國分寺は・・。
で、奈良時代や平安時代に先ほどの三郷地域の長者原に國府が在ったとすると、ざっと六・七百年のその間の、いずれかの時期には既に日本海側の岩殿山辺りに移っていた、とそうお考えなわけですね先生は・・。
あ、ところで三郷地区というのはどの辺りに成るんでしたっけ・・」私はそう言って、ウエストポーチから上越地区の簡易な観光MAPを取り出して二人に示し、尋ねた。
先生は眼鏡を押し上げて裸眼でじっとMAPを見て、新幹線の上越妙高駅の二・三㎞ほど北東側に在る、関川と櫛池川とに挟まれた一画を指さした上で、
「ここが三郷の長者原で、ず~っとこっちの日本海のヘリに在るのが岩殿山と郷津になるです・・」と言って、北西の五智国分寺の左側の日本海に面した山を指さし、次いで麓の海岸沿いを指さした。
「これはまたずいぶんとまぁ、離れてますね。高田平野の真ん中ら辺からこっちは日本海側ですもんね。ざっと直線で十㎞ってとこですか、両者の距離は・・。
ん?でもここって『菅原ノ牧』に割と近い場所なんですね、三郷地区というのは・・」私がそう言うと、
「そうだ、『菅原ノ牧』はこの櫛池川の上流に在るダスケ・・」小柄な男性が言った。
「なるほどそうでしたか、官営牧き場の『菅原ノ牧』が後背地に控えているんですね・・。ん~ん、そうですか・・。ひょっとしてこの近くに『馬主神社』とか『駒形神社』といった馬にちなんだ神社とかは在りませんか?」私は呟いた。
「馬にちなんだ神社は知らんケンド『馬屋(まあ)』とか『荒牧』とかいう場所は在るだよ」小柄な男性が教えてくれた。
「お詳しいですね・・。因みにマアとはどんな字を書くんですか?」私が彼に尋ねると、
「マアは馬屋って書くだよ。オラほはそっから割と近くの野尻ってとこだでな・・」小柄な男性が応えた。
「そうでしたか・・。ありがとうございます。奈良時代や平安時代の頃に國府が在った『三郷の長者原』の後背地に『馬屋』や『荒牧』地区があって、その先というか更に奥には『菅原ノ牧』が在ったわけですね・・。
ん~ん、しつこいようですがホントに馬絡みの神社は在りませんでしたか・・」私はもう一度食い下がって尋ねた。
「聞いたことねぇな・・。『菅原神社』や『武士(もののふ)神社』は在るどもな・・」
「『モノノフ神社』ですか?それって物部氏のモノノフですか?『菅原神社』は菅原道真だとしても・・」私が確認すると、
「いや『武士』って書いてモノノフって読むんだぁ」小柄な男性が言った。
「はぁ『武士』のモノノフでしたか・・。すると祭神は応神天皇かなんかで、八幡神社系ですかね?」私が推測を交えてさらに尋ねた。
「いんや違うド、確っか神様はウマシマシの命さんだったべや」彼は否定した。
「確かその神様は、物部氏の先祖神だったかと・・」ヒゲの先生はそう言って補完した。
「そうでしたか、いや武士のモノノフなら武人の神様『八幡様』かなと思ったんですがね、違いましたか・・そうですか・・。
しかしあれですよね、その武士という集落は馬屋とか荒牧の近くで、長者原とも近いんでしたよね・・。ん~んこの地図だとどの辺りに成りますか?そのモノノフの場所は・・」私はモノノフの集落の事が気に成って、更に確認した。小柄な男性はMAPをちょっと凝視してから、
「ここら辺りだ・・」と言って指さした。
「ほう、この辺ですか、ちょうど『長者原』と『荒牧』『馬屋』とのほぼ中間的な場所に成るんですね、なるほどね・・」
私はそう言って県道30号線近くのモノノフの場所が、かつて國府・國衙や國分寺があったのではないかとされる三郷地区と「荒牧」「馬屋」とのほぼ中間のエリアに在ることを確認してから言った。
「これはまぁ推測ですが、國衙・國分寺がかつて在ったんではないかとされる三郷地区と、『菅原ノ牧』を後ろに背負った『荒牧』や『馬屋』の中間にモノノフすなわち武士たちの集落があったとすると、國衙や当時の府中に仕えていた『騎馬武者達の集落』だと、そんな風に考えることは出来ませんか?とりわけ、鎌倉時代の武士の時代であれば尚の事・・。
更に鎌倉幕府の初代守護であった安田義資公であれば、まずは國府の近くに拠点を固めたでしょうからね、それに基本彼らは騎馬武者ですから牧き場の近くに自分たちの拠点を作ったと、そう考えても好くありませんか・・。
尤もこの時点でもなお、國府や國衙が当初の三郷地区にまだ在ったとすれば、ですけどね・・」私は、手元のMAPを指さしながらヒゲの先生に向かってそう言い、彼の反応を待った。先生はじっと考えていた。
「日本海側の『直海ノ牧』やこちらの『網ノ子ノ牧』糸魚川の『羽生ノ牧』とは違って、國衙や國府に直結する武士団のための牧き場や馬屋がこうやって背後に控えていたのが、ここ『菅原ノ牧』エリアの当時の都市計画的な構成だったんじゃないかって、そんな風に思えちゃうんですよね、私には。まぁあくまでも義資公の立場に立つと、ですけどね・・」私は更に迫った。
「確かに、そう考えることは出来るかもしれないですね・・」ヒゲの先生はそう言ってから、話を続けた。
「それにこの県道30号線は『柿崎・新井線』ってせう云って、かつての『直海ノ牧』の在った柿崎地区につながる昔からの幹線道路で、その間には『保倉ノ牧』も在ったですよ・・」ヒゲの先生はそう言って、MAP上に「保倉ノ牧」辺りを指し示して、私の仮説を補完してくれた。
『 吾妻鏡 第六巻 』文治二年(1187年)五月二九日
:『全訳吾妻鏡1』298ページ(新人物往来社)
「神社仏寺興行の事、二品(源頼朝)日来思し召し立つの由、かつは京都(朝廷)に申さるるところなり。
かつは東海道においては、守護人等に仰せて、その國の惣社ならびに国分寺の破壊、および同じく霊寺傾倒の事等を注さる。これ重ねて奏聞を経られ、事の體(てい)に随ひて修造を加へられんがためなり。
三好善信・藤原俊兼・藤原邦通・二階堂行政・平盛時等を奉行として、今日面々に御書を下さると云々。」
註:( )は著者記入
『吾妻鏡』にも明らかなように、平安時代や鎌倉時代初期においては、奈良時代に建てられた神社仏閣や国分寺は、創建以来四・五百年は経過しており地震や台風などの自然災害や風雪、更には戦乱などによって少なからぬ物理的な損傷があった事が窺われる。
そのような事があって頼朝は東海道の各国の守護に命じて、その損傷の状態に応じた修造や修築をそれぞれに奉行(執行者)を立て、執行するよう命じている。
従って、北国道の越後之國においても国分寺や惣社(府中八幡等)に関して、守護である安田義資に同様の沙汰が、直接または間接的にあった可能性は否定できない。

< 越後之國、頚城郡古図 >
「あのヨ、ちょっといいだかい。オラほの野尻も県道30号線近くに在るだよ・・」小柄な男性がそう言って指でテーブルの上のMAPをなぞった。
「せ云えば、おまんた(あなた)の処には八幡様がなかったかい?それと元屋敷って部落も・・」ヒゲの先生が小柄な男性に向かって言った。
「ソダ、八幡様在るきゃ。稲の『正八幡神社』ってせ云うだ。元屋敷は道路の向こッ側だ、今は田んぼに成ってるすけどな・・」彼はそう言って同意した。更に、
「隣の部落に成るだども、高津にも八幡様あっど・・」と付け加えた。
「国道405号の方だったか?」先生が言った。
「ソダ、『牧村』の方さ行く道だ」と彼は応えた。
「えっ『旧牧村』ですか?上牧や猿ケ馬場の在る?」私は牧村と聞き、昼前に上越市埋蔵文化センターで聞いた上牧地区や猿ケ馬場の事を思い出した。
「ソダ、だいぶ上がってかねば成らねどもな・・。したっけ猿ケ馬場って聞いたことねぇど、オラ・・」小柄な男性は上牧のことは認めたが猿ケ馬場の事は知らない様だった。
「確か棚広新田の山の上の方だそうです、猿ケ馬場は・・」私はメモを見ながら説明した。小柄な男性は首をかしげていた。どうやら猿ケ馬場の事は知らない様だった。
「高津の八幡様は、確か鶏を祀ってるってせ云った珍しい八幡様だっけな・・」ヒゲの先生が思い出したようにそう付け加えた。小柄な男性は肯いた。
「えっ、鶏を祀ってる八幡様ですって?それ、もう少し詳しく教えてもらえませんか?」私は鶏と聞いて黒川衆の金の鶏の事を思い出し、早速聞いてみた。
「ソダ、本殿には確かお釈迦さんと平安時代のお公家さんの恰好した神様の像が一つずつ在って、真ん中に確か鏡が在っただ。ほの手前に狛犬みたく二羽の鶏の木像とが在ったド・・」彼は記憶をたどりながらそう教えてくれた。
「本殿の中に、ですか?木造の鶏が阿吽の様に向かい合っていたとか、ってことですか・・」私は興奮してそう言った。
「ソダ、鶏だ。ほれに関係アッか判らねども、高津の八幡様の氏子衆は鶏を飼ったり、食ったりしたらナンねぇってしきたりがあるど・・。神様の使いダスケ、ってせって(そう云って)・・」小柄な男性はそう言って高津地区の氏子達に伝わる鶏との関係を話してくれた。
「う~ん、そうなんですかぁ」私はそう言って唸ってしまった。そしてじっくり考えてみた。上牧や猿ケ馬場に向かう国道405号沿いに在る「高津八幡神社」の事を、である。本殿には神や仏の神像と一緒に鶏が祀られているという。しかも八幡神社の中に、なのだ。
「その仏様は釈迦如来であって、十一面観音像ではないんですね?」私は、小柄な男性に詳しく聴いてみた。
「ソダ、お釈迦様だ。十一面観音せったら頭に顔がイッペコトついてる観音様だべ?」彼の問いに私は肯いた。
「いんや違うド、オラが見たんは蓮の花の上に胡坐かいてるお釈迦様だ、うん間違げねぇ」と彼はきっぱりと断定した。
「何かあるですか?」ヒゲの先生が私に聞いてきた。
「いや、実はですね。鶏というのは先ほど言いましたが、金山開発を担う職能集団である金山衆の崇拝する神様が、実は鶏なんですよ。
彼らの本拠地である黒川金山の在る山が『鶏冠山』と言いまして、その山の頂上が鶏のトサカの形をした山でして・・」私はそう言って、黒川衆と鶏冠山の関係を説明した。
「黒川衆にとって、鶏は神聖な存在で『金山まつり』の時は金の鶏のご神体を神輿に担いで鶏冠権現神社の里宮から二㎞近く山を登って、頂上の奥宮の鶏冠神社まで練り歩くんです。
それに例の京都の祇園祭でも、彼らが始めたと思われる『綾傘鉾』のご神体もまた金の鶏でしてね、とにかく金山衆と鶏とは切っても切れない関係でして・・。
ところでその高津の八幡神社の本殿には神や仏の像と一緒に、そうやって鶏が祀られているわけですよね・・。
更に鶏を飼う事やその肉を食べることがタブーとされてもいるんですよね、その氏子さん達の間では・・」私はそう言って二人の顔を見た。小柄な男性は肯いた。私は話を続けた。
「なるほどね~。その県道30号線の『新井・柿崎線』でしたっけ?その街道というか南北のラインが、どうやら騎馬武者守護の安田義資公にとって、非常に大きな意味を持っていた当時の都市計画上の主軸というか、南北の都市軸の幹線道路のようですね・・。
背中に『菅原ノ牧』を背負いながら、北の日本海側には『直海ノ牧』が在りその途中には『保倉ノ牧』も在る。
しかも国道405号線と交わる野尻と云いましたか、その辺りには『稲の正八幡神社』と『高津八幡神社』の二つの八幡様が在って、更にその近くには元屋敷が在り、高津の八幡神社では鶏を祀っていると。
これだけでもすごい事なんですけど、更にその野尻で交わる405号線を東方向に遡ると『上牧地区』や『猿ケ馬場』まで在るんですよね。いずれも牧場や馬に関係した地域ですよね・・。
一方その県道30号線を更に南に下ると『武士地区』が在って、『荒牧』『馬屋(まあ)』と『國府・國衙』の在ったと思われる三郷地区とを東西に結ぶ道路の、ほぼ中間エリアにその『武士地区』が在るって事ですよね。う~ん・・これはもう、ほとんど決まりですね・・」と私は言った。
「といいますと?」ヒゲの先生が改めて聞いてきた。
「えぇ、今の情報を整理するとこんな事が言えるのではないかと、私は想います」私はそう言ってビールをぐっと飲んで、喉を湿してから自説を話始めた。
「まず鎌倉幕府の源頼朝から初代の守護に任命された安田義資公は奈良時代から國府・國衙の在った長者原の三郷地区を拠点にして、現在の主要地方道『新井・柿崎線』の県道30号線沿いに、騎馬武者用軍馬のための牧を造ったのではないかと。
あるいは逆に奈良・平安時代から在った官営牧を繋ぐ幹線道路を、造ったのではないかと思われます。
そして自らは野尻の元屋敷辺りに館か何かの拠点を造り居住し、自らの屋敷近くに源氏の氏神でもある稲の『正八幡神社』を創り、祀ったのではないだろうかと思われます。
更にその義資公の拠点の館近くには、金の鶏を神として祀る黒川衆の集落が在り、彼らは高津八幡神社を創って祀ったと。
一方その義資公に仕える騎馬武者の家来達は『武士地区』周辺に居住し、そこが拠点と成った。そしてその背後に古代から在った『菅原ノ牧』との間には、『馬屋』や『荒牧』といった軍馬の育成や飼育の拠点を造ったのではないか、と考えられるわけです。
更にその拠点とそれぞれの牧とを結ぶ南北の主軸の幹線道路を造り、その南北の主軸に交わる東西の重要な軸として、現在の国道405号につながる街道を野尻辺りでも造ったと。
それと同じ考えでその南北の主軸に交わる東西軸を、『菅原ノ牧』と國衙・國府の在った『三郷地区』を結ぶ幹線道路にも造ったのではないかと、そんな風に思われるわけです。
その二つの軸が交わる結節点が先ほど来の『野尻地区』や『武士地区』に成ったんではないかと、私にはそんな風に想うことが出来るんです・・」私は手元のMAPを使いながらそう言って説明した。
「なるほどですね・・。でもまぁ、國衙と菅原ノ牧とを結ぶ東西軸は安田義資の入部前、國衙や國府が三郷地区に造られた奈良の時代から在ったのではないか、と私は想いますけどね・・。
因みに今の県道198号線ですね、その東西の軸は・・」ヒゲの先生は私の長い仮説を聞き終えると、冷静にそう言ってから、
「やはり、騎馬武者用の軍馬が前面に出てくるんですか、安田義資の越後之國にあっては・・」と付け加えた。
「ハイ騎馬武者用の軍馬の存在が、キーに成るんです。甲斐源氏は騎馬武者が生命線ですからね・・。確かにおっしゃるように義資公の入部以前かもしれませんね、その今の県道198号線が出来たのは・・。
まぁその方が自然かもしれないですね何しろ國衙があった場所ですもんね・・。
しかし従来の人の往来が中心だった道路を、騎馬武者が疾駆しやすいように整備した可能性はあると思うことは出来るかもしれませんよ・・。一種の道路の規格をワンランク上げた、というか・・」
私はその時、戦国時代の武将武田信玄が甲斐と信濃・上野を結ぶ棒道と云われた、騎馬武者往還のための幹線道路を造ったことを頭に描きながら、そう言った。
「せ云えば柿崎のほうの『直海ノ牧』の近くには『馬正面』って交差点が在るんけど、ほれもやっぱり馬絡みだべか?」小柄な男性が言った。
「ほう、『馬正面』ですか・・なんだか面白そうですね。その県道30号線沿いに、ですか?それって名前からして、明らかに馬絡みっぽいですね」私はそう言ってニヤリとしてから、話を続けた。
「それに『直海ノ牧』につながる南北軸に在るわけですよね、その『馬正面』という場所は・・」私がそう言って肯定すると、彼は肯きながら観光MAP上で、その辺りの場所を指し示した。
「ん~ん、実はですね立花さん、ひょっとしたらもう一つの東西軸と云って良いかもしれない場所が在りましてね、その県道30号線の南北の主軸にも架かって来るんですがね・・」ヒゲの先生はそう言って私の顔を見て、MAPでその場所を指し示しながら言った。
「ここなんですがね、浦川原区飯室地区って云うですが、ここで巨大な馬屋の遺跡が発掘されているですよ、今から二六・七年前の平成三年頃の事ですがね・・」
先生がそう言ってMAPに示した先は、「ほくほく鉄道」という東西に走るローカルな鉄道から南下したエリアで、ほぼ保倉川沿いと云っても良い場所であった。MAPには国道253号と書いてあった。
「浦川原の馬屋遺跡の事だべか?」小柄な男性が反応した。ヒゲの先生は肯きながら私に、
「確かそこには六棟の馬小屋が整然と並列に並んでいて、各棟にはそれぞれ十二房の仕切られた区画が在ったと記憶してます。
各房はそれぞれ二坪四畳分のスペースが在って、六棟合計七十二房、従って72頭の馬が常時飼育されていたと推測できる、厩の跡なんです」そう教えてくれた。
「それはすごい!一か所で72頭分の厩が在ったんですか・・。因みにそれはいつ頃の遺跡だと・・」私はその新しい情報に驚きながらも、期待を込めてその馬屋遺跡の年代を尋ねた。
「遺跡から出た出土品は、甕や壺などの須恵器や珠洲焼のすり鉢や甕が出てきたと記憶してます。平安後期から鎌倉時代に掛けてのモノらしいです」ヒゲの先生はそう言って顎髭をしごいた。
「ほぅ、ドンピシャですね義資公の時代に・・。その厩の建て主とかは特定されているんですか?」私が尋ねると先生は、
「当時の遺跡についての報告書に具体的な事は書かれてませんだが、鎌倉時代初期の『土豪の私的な牧』の一つだったのではないか、といった様な事が書かれていたように記憶してます。
しかしまぁその時の遺跡の平面図や想像図を見て、とてもそこらの土豪の私牧じゃぁ無いだろうって、オラはせ(そう)想ったですよ。あまりにも整然としてましたからね・・」と応えた。
「そうでしたか、そんな遺跡が在ったんですねこの保倉川の辺りに・・」私はそう言ってその遺跡が現れたという旧浦川原村飯室の「境原遺跡」の場所をMAPに印し、メモ帳に書き記した。
「浦川原村って今では上越市と合併してるんですよね・・。因みに当時の遺跡の記録はどこかで閲覧することは出来ますか?」私はそう言って先生に尋ねた。
「直江津の図書館か高田の図書館に行って、『浦川原村の文化財』せ云った本を探してみてきなっせ、ほれに書いてあったですよ確か・・」先生が教えてくれた。
「直江津図書館ですね・・」私がそう言うと、先生は壁側を指さして、
「駅前のホテルのすぐ裏手に在るですよ、ここから二・三分・・」と教えてくれた。
「あ、そうですかそんなに近いんですか、そしたら早速明日にでも行ってみます」私はそう言って、明日にでも行ってみる事にした。
「そうすると先生は、その『境原遺跡』は地方の豪族の私牧の馬屋レベルでは無いって、そう思ってられるんですね・・。
・・では改めてお聞きしますが、さきほどからの私の推測を聞かれていて、どう思われましたか?その関連性というか・・」私はヒゲの先生の心の中を探るように、じっと見つめた。
「少なくとも土豪の有力者よりは、越後之國の守護の方が納得は行くかな・・」先生はそう応えて、ぐい吞みをあおった。私はそれを聞いて更に言った。
「実は義資公の父親の安田義定公には五奉行と云っても良い、有能な家来衆がおるんですが、その中に『前(さきの)右馬(うまの)允(じょう) 宮道遠式』という武将がいるんですよ。
その宮道遠式は朝廷の官営牧の管理を任されていた、今でいえば局長クラスの人物だったんですよね、右馬の允ですからね。
そして彼はどうやら甲斐之國を初め遠江之國、更にはここ越後之國を含めた義定公親子の領国の馬事担当の奉行だったのではないかと思われる人物でして・・。
その宮道遠式が官営牧で培ったノウハウを基に、その浦川原村境原の厩を造ったと考える事は出来ませんか?飛躍してるかもしれませんが・・」私はそう言って再度先生の顔を覗き込んだ。先生はじっと考え込んだ。
「あ、それから因みに宮道遠式は、確か物部氏の流れをくむ一族だったようです。先ほどの『武士地区』と関係があるのか、無いのか判りませんが・・」私はそう言って、宮道遠式について説明した。
「前右馬允宮道遠式、ですか・・物部氏の一族でもある『前の右馬の允』なんですね。ん~ん確かに朝廷に使えた身分ですネその役職でしたら・・」先生はそう言って、宮道遠式のかつての官職の事をしばらく考えていた。そして、
「まぁ、軽々には語れませんが・・。地方の土豪の私的牧き場よりは、可能性ありそうですかね・・。う~ん『新井・柿崎街道』がね・・、そう言った役割を担っていたと・・。更に國府や國衙にも絡んでくると・・、初代の守護安田義資がねぇ・・」
そう言ってしばらくヒゲの先生は腕組みをして、考え込んだ。これまでの話をじっくり咀嚼している様であった。
私はそれを機に席を外し、トイレにと向かった。
『 境原遺跡 』 平成16年12月20日発刊
『浦川原村文化財』35ページ(浦川原村教育委員会)
平成3年6月、浦川原村の工業団地西部事業に伴う確認調査で、地表下20~40㎝から平安時代(九~十世紀)と鎌倉時代(十三世紀頃)の二時期の柱穴・溝・井戸等の遺構を発見した。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
各建物は基本的に桁行二十四間、梁行二間で、棟通りには二間ごとに間仕切りの柱がある。
これより1棟の建物は十二の房(1つは4畳分)に分けられ、収容した馬の頭数が具体的に推定でき、牧の経営規模を解明する上で高い学術的価値がある。
当該報告書には、上記のような解説と共に「境原遺跡平面図」及び「境原遺跡想像図」の二種類の挿絵・図が記載されており、六棟各十二房が描かれている。

凡例:黄色は集落、北から「馬正面」「野尻」「元屋敷」「高津」「武士」「荒牧」「馬屋」
:赤色は「長者原/三郷地区」、国衙・国分寺跡
:緑色は牧き場等、北から「直海ノ牧」「境原馬屋遺跡」「菅原ノ牧」